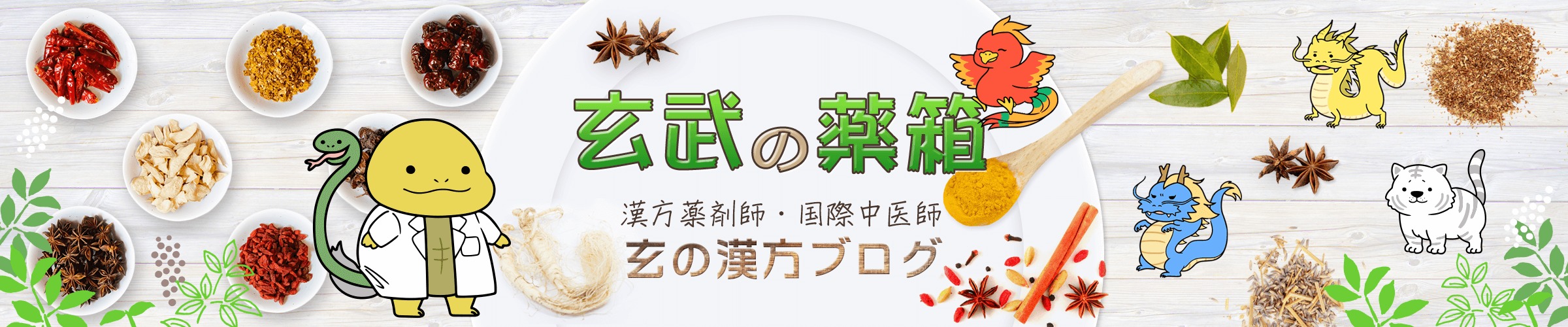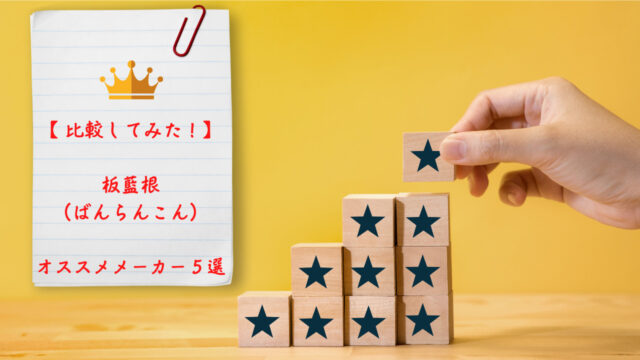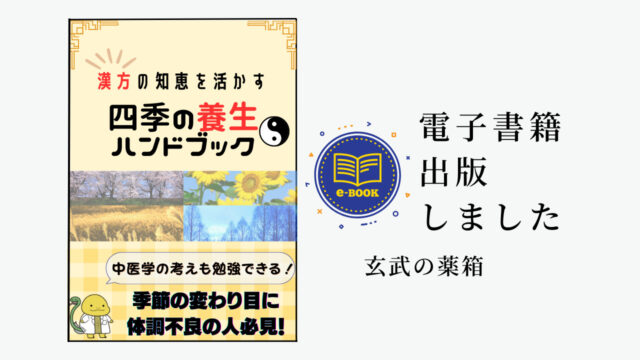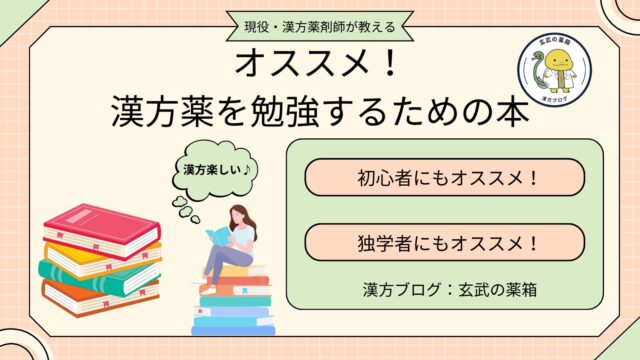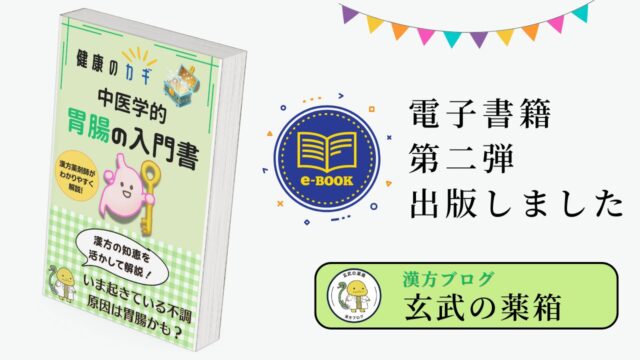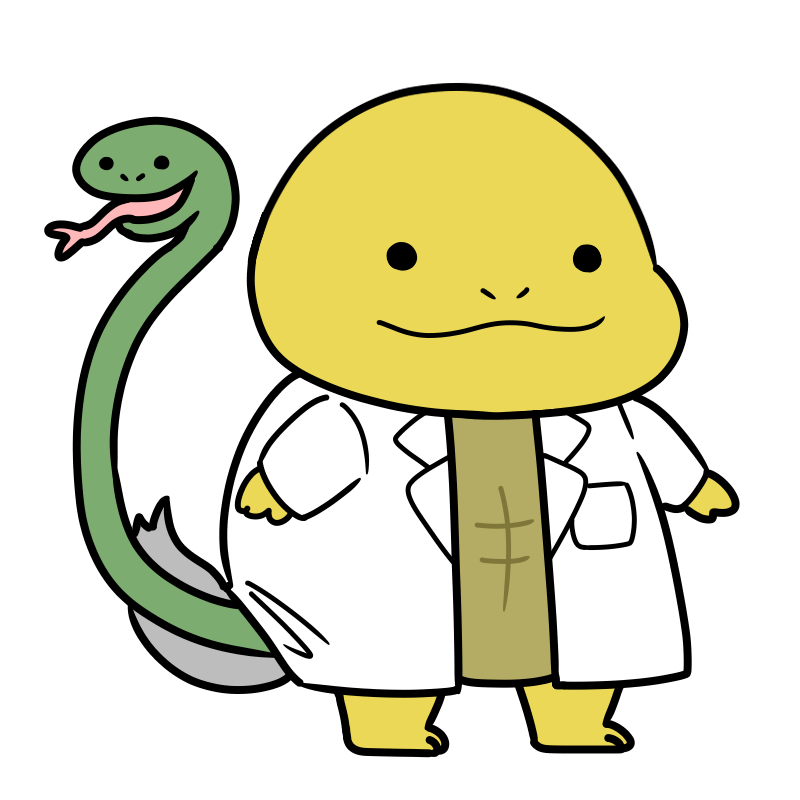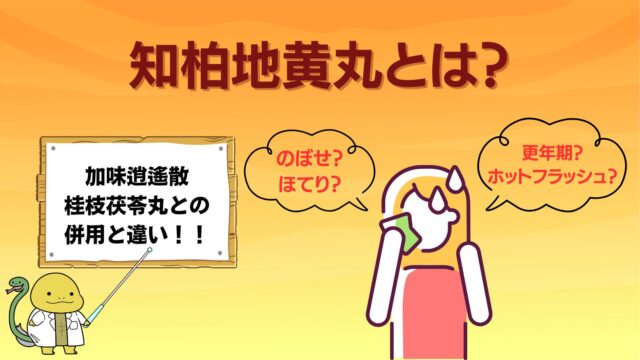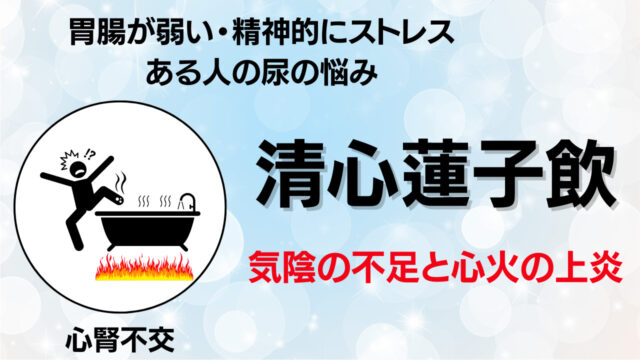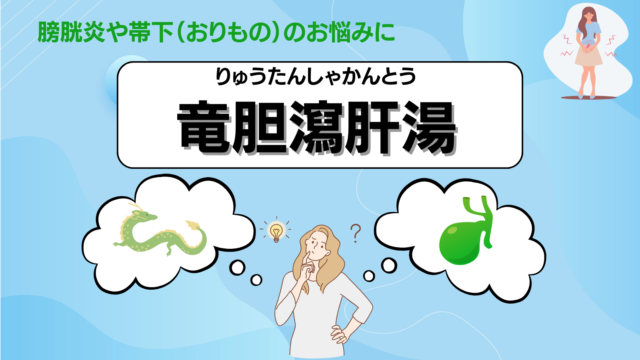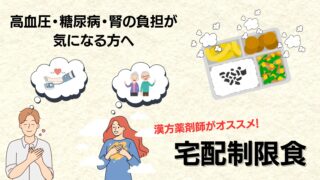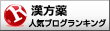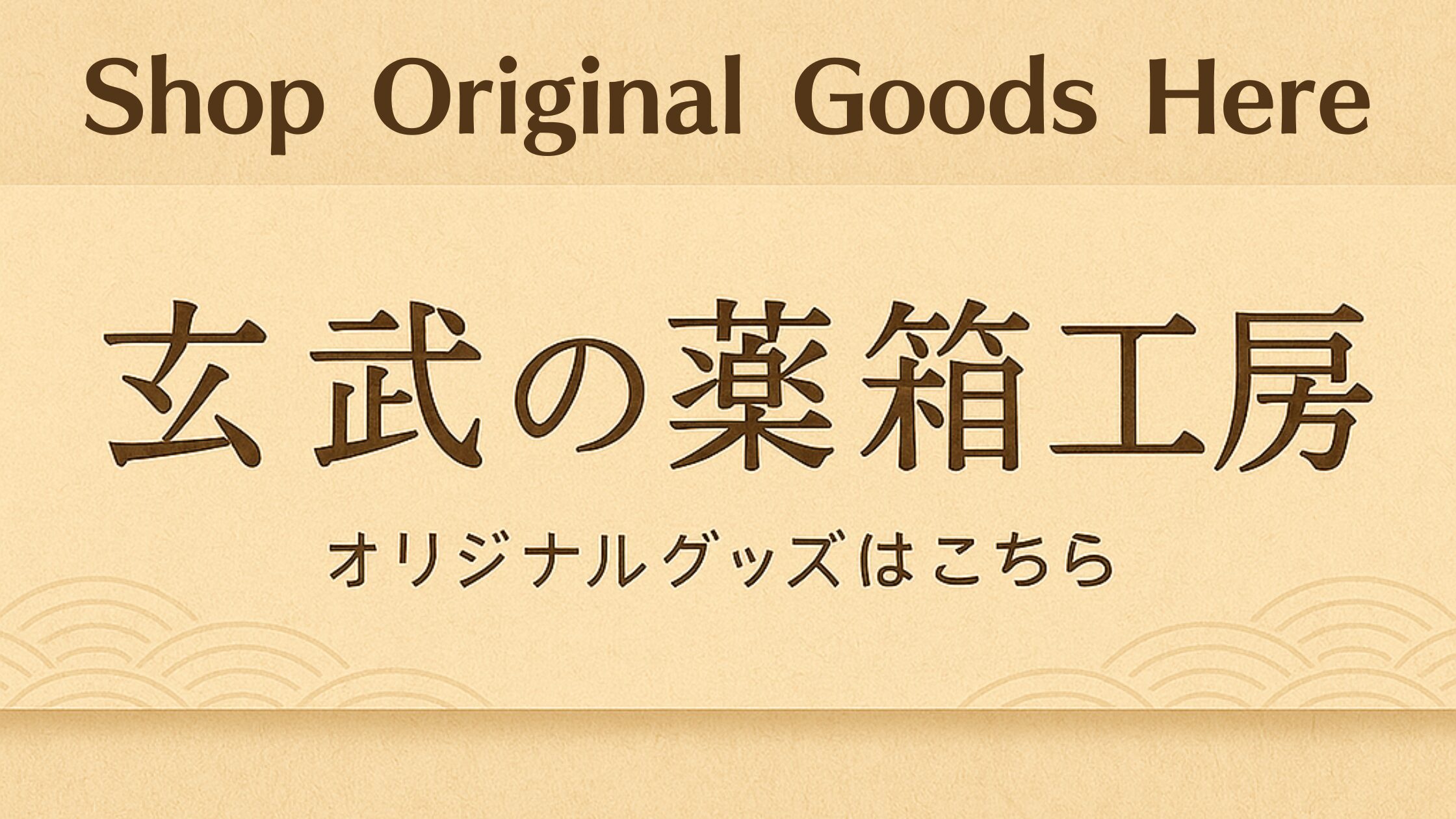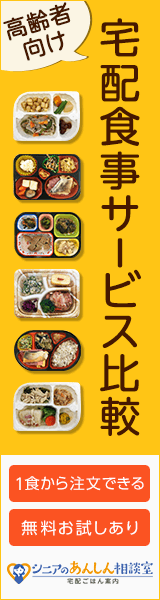【膀胱炎・頻尿・残尿感】猪苓湯とは?効果や、飲み方・五苓散との違いを漢方薬剤師が解説!
ちょっと熱っぽいし。
みなさん、こんにちは!
漢方薬剤師の玄(@gen_kanpo)です。
膀胱炎の痛みや頻尿って、つらいですよね。
最近は、仕事柄トイレに行けない人も多く、頻尿に加えて「膀胱炎」のご相談も増えてきました。
そんなとき、漢方の選択肢に挙がるのが「猪苓湯(ちょれいとう)」です。
今回は、排尿トラブルに使われるこの漢方薬について、詳しく解説していきます。
- 膀胱炎を繰り返している
- 頻尿や残尿感がある
- 猪苓湯を飲んでいるが効果が感じられない
猪苓湯ってどんな漢方薬?


簡単に説明すると
余分な水分(湿)と熱を取り除き、排尿トラブルを改善する処方です。
利水作用のある生薬をベースにしながら、熱による炎症や、潤いの不足にも配慮されています。
出典となる『傷寒論』には、
「(陽明病で下剤を使った後)もし脈が浮いて発熱し、のどが渇いて水を欲し、小便の量が減るときは、猪苓湯を用いる」
また、『金匱要略』の「淋病篇」には、
「脈浮、発熱し、渇して水を飲まんと欲し、小便利せざれば、猪苓湯これを主る」
とあり、同様の状態が記載されています。
※ここでいう「淋病(りんびょう)」とは、現代の性感染症とは異なり、排尿痛や残尿感、尿が出にくいといった下部尿路の不調全般を指します。
つまり、「発熱・のどの渇き・尿が出にくい」といった症状がセットで現れたときに、猪苓湯が適していると古典では示されています。
このような状態を、中医学では「水熱互結」と呼びます。
もともと体内にたまった水湿(すいしつ:余分な水分)に、「風寒」の邪気が加わって熱化し、その熱と水分が結びついて体内で滞ってしまうのが「水熱互結」です。
背景には、五苓散が使われるような「水滞(すいたい)」=水分代謝の乱れがあり、さらに熱邪(ねつじゃ)が重なって複雑化した状態といえます。
猪苓湯は、湿熱の邪が腎・膀胱の作用を低下させ、排尿困難や排尿痛を引き起こす場合や、熱の邪気がさらに深く入り込み(血の中に)血尿を引き起こすときにも有効とされます。
そのため、以下のような症状に良く使う処方です。
- 尿が出にくい
- 口の渇き
- 体の熱感、発熱
- 排尿時の違和感や痛み、血尿など
構成生薬
| 猪苓(ちょれい) | 利水作用により、体内の余分な水分を排出しやすくします。 |
|---|---|
| 茯苓(ぶくりょう) | 胃腸の働きを助けながら、水分代謝を促す「健脾利水」作用があります。 |
| 沢瀉(たくしゃ) | 利水作用に加え、体内の余分な熱を冷ます働きもあります。 |
| 滑石(かっせき) | 尿の通りを良くする利尿作用と、清熱解暑(暑さを冷ます)作用を持ちます。 |
| 阿膠(あきょう) | 補血・止血作用があり、体液を補って他の生薬による消耗を防ぐ役割があります。 |
この処方は、不要な水をさばきつつ、熱を冷まし、陰液(体液)を補うという、一見バラバラな作用がバランスよくあわせ持っています。
阿膠は二つの意味で特徴的で、熱による潤いの消耗を防ぎながら、血尿にも対応する処方になっています。
【五苓散との違いは?】
五苓散から朮(蒼朮or白朮)と桂枝(けいし)が除かれ、滑石と阿膠が加わったのが猪苓湯です。
- 五苓散:浮腫み、風邪の初期、頭重感など「水の滞り」によく使う
- 猪苓湯:そこに熱が加わったときの排尿トラブルに対応する
桂枝は、体表を温めて発汗を促すだけでなく、気血の巡りを良くし、特に上部に滞った水分や気を動かす働きがあります。
桂枝を含む五苓散には、頭部の水滞による頭痛・頭重感・めまいなどに対応する効果が期待できますが、猪苓湯にはこの桂枝が含まれていないため、こうした頭部症状にはあまり適していません。


よく使う症状


体力に関わらず使用でき,排尿異常があり,ときに口が渇くものの次の諸症:排尿困難,排尿痛,残尿感,頻尿,むくみ
厚生労働省「薬局製剤指針」より引用
排尿痛(血尿にも対応)
猪苓湯に含まれる阿膠(あきょう)には、補血・止血の作用があります。
このため、単なる排尿痛だけでなく、膀胱炎による出血を伴うタイプ。
いわゆる血尿を伴う場合にも、症状の緩和が期待できます。
炎症度合いが高さで使い分けが重要です。
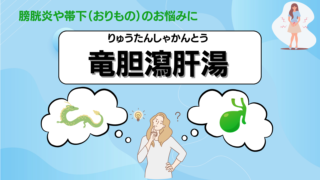
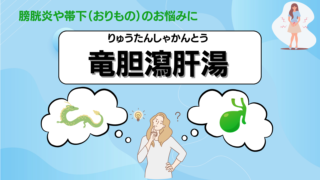
浮腫み(むくみ)
実は、猪苓湯は「むくみ」にも非常に使いやすい処方のひとつです。
特に、熱を伴ったむくみ(=水熱互結)に適しており、体内にこもった熱と余分な水分の両方を取り除くことで症状を改善します。
冷えて浮腫むタイプには、当帰芍薬散や五苓散など体質に応じた処方を使いますが、猪苓湯は「熱と水の停滞」によるむくみをさばくのに適しており、夏場の火照りやのぼせを伴うむくみに活用できます。
たとえば
「クーラーの中にいると身体が火照る」
「暑いのにトイレの回数が少ない」
そんなタイプの浮腫みにも、体質が合えば役立ちます。
残尿感・尿が出にくい
猪苓湯には、猪苓・茯苓・沢瀉・滑石といった利水作用に優れた生薬が多く含まれており、体内の余分な水分を排出する働きがあります。
とくに滑石(かっせき)は、「滑る石」という名前の通り、尿の通りをスムーズにする作用があり、排尿困難や残尿感の改善に効果的です。
注意点


長期での使用は注意
「体力に関係なく使える」とはいえ、猪苓湯は基本的に短期で使う処方です。
長期服用すると、陰液や血が消耗されてしまうおそれがあります。
特に血虚(けっきょ)や陰虚(いんきょ)タイプの方は、体に必要な潤いや血が不足しているため、単独での長期使用は注意が必要です。
このような体質の方や、症状が慢性化している場合には、補血作用のある「四物湯(しもつとう)」を組み合わせた「猪苓湯合四物湯(ちょれいとうごうしもつとう)」という処方が適しています。
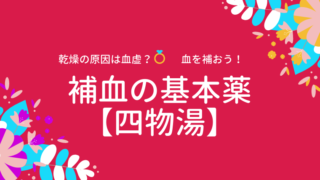
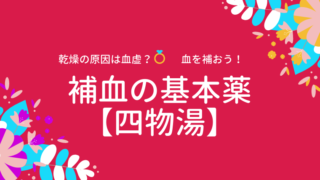
口の渇きが強い場合は注意
口の渇きがあるからといってすぐに猪苓湯を使うのはNG。
熱が強く、すでに体液が失われているタイプでは、猪苓湯を使うと、かえって乾きを強めてしまうことも。
この場合は、白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)など、熱を去り津液を補う処方が向いています。


まとめ
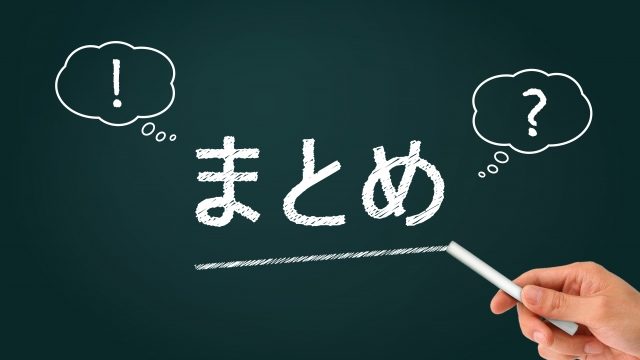
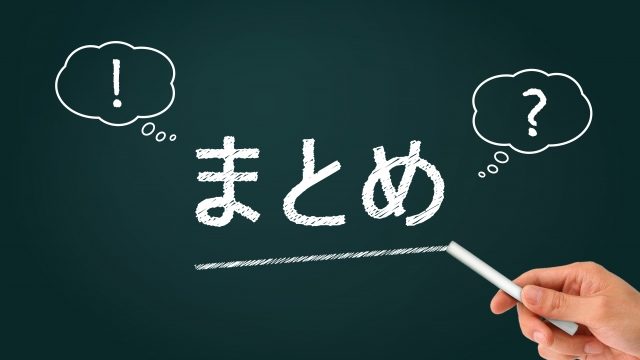
今回は、排尿痛や残尿感によく使われる漢方薬「猪苓湯」についてご紹介しました。
排尿トラブルが起きやすい方は、体質や症状に合わせて、検討してみてもよい処方です。
今回の内容を簡単にまとめると
猪苓湯は不要な「水」と「熱」を取り除き、排尿痛・残尿感を改善する処方。
【よく使う症状】
- 排尿痛(血尿)
- 残尿感
- 尿が出にくい
【注意すべき点】
- 長期服用には注意(陰血の消耗)
- 口の渇きが強いときは体質に応じた処方を検討する
トイレの我慢も膀胱炎の原因になるから気をつけてね。