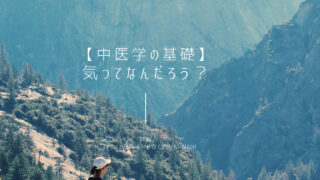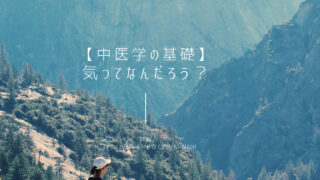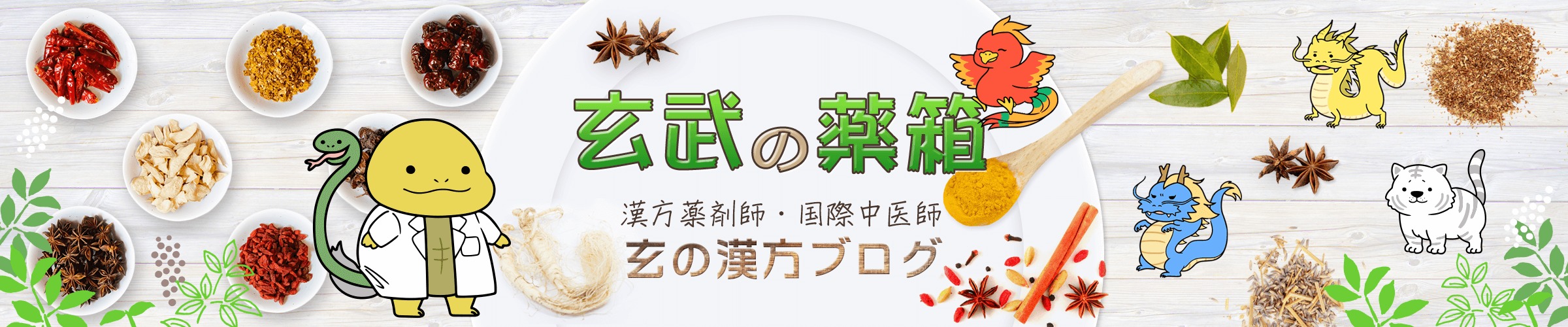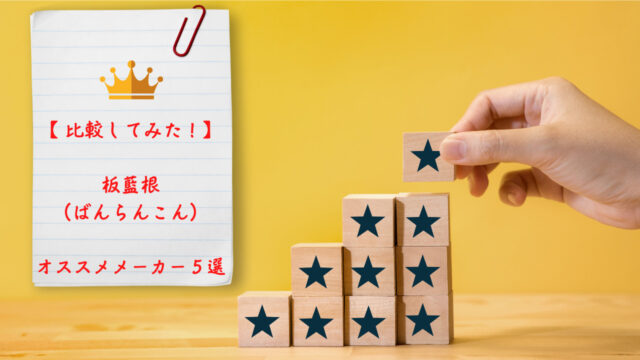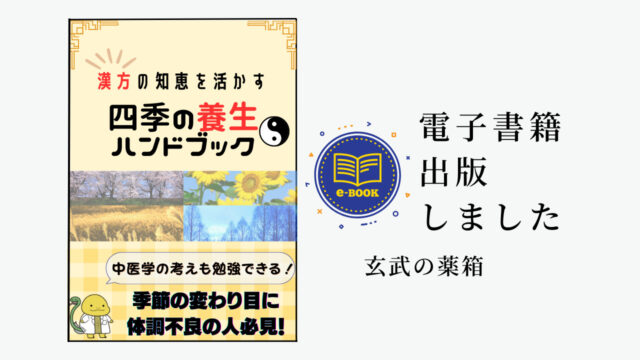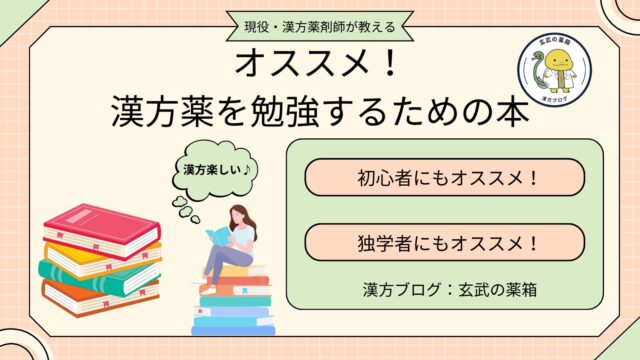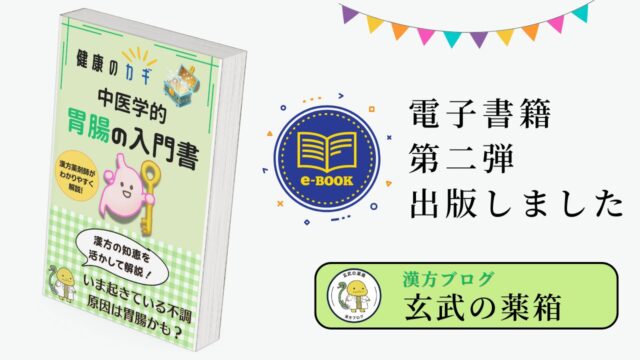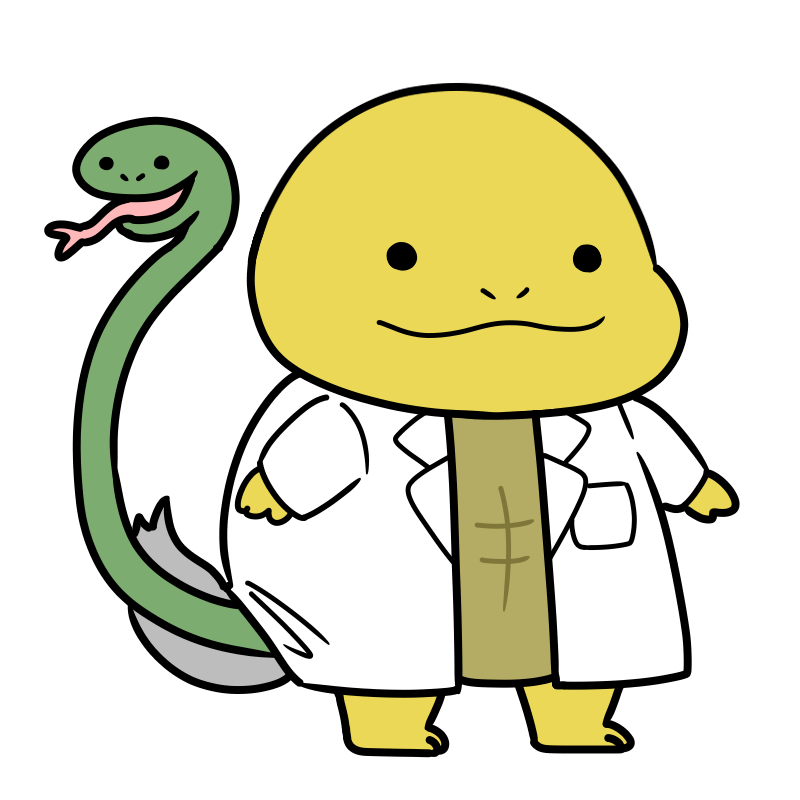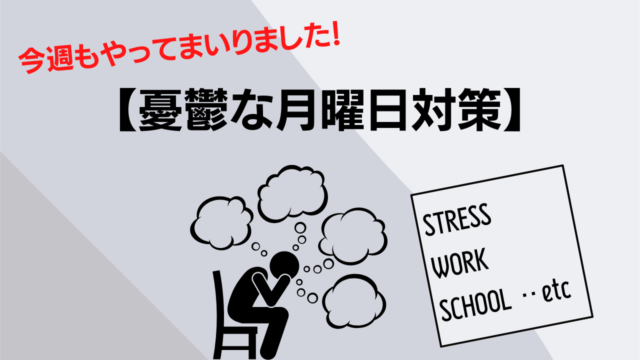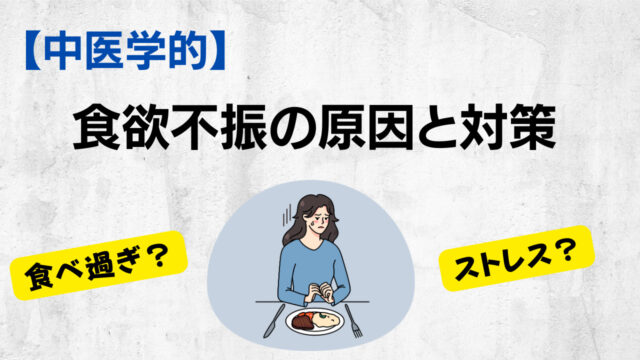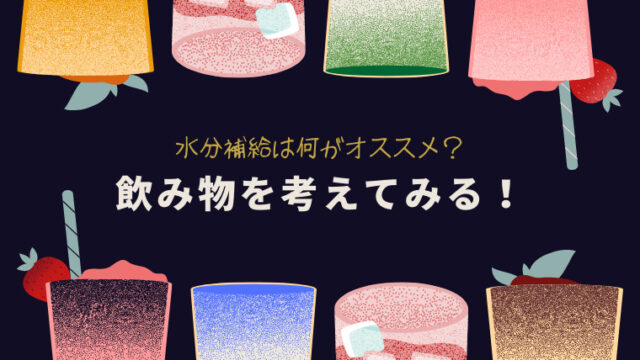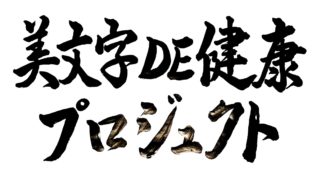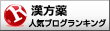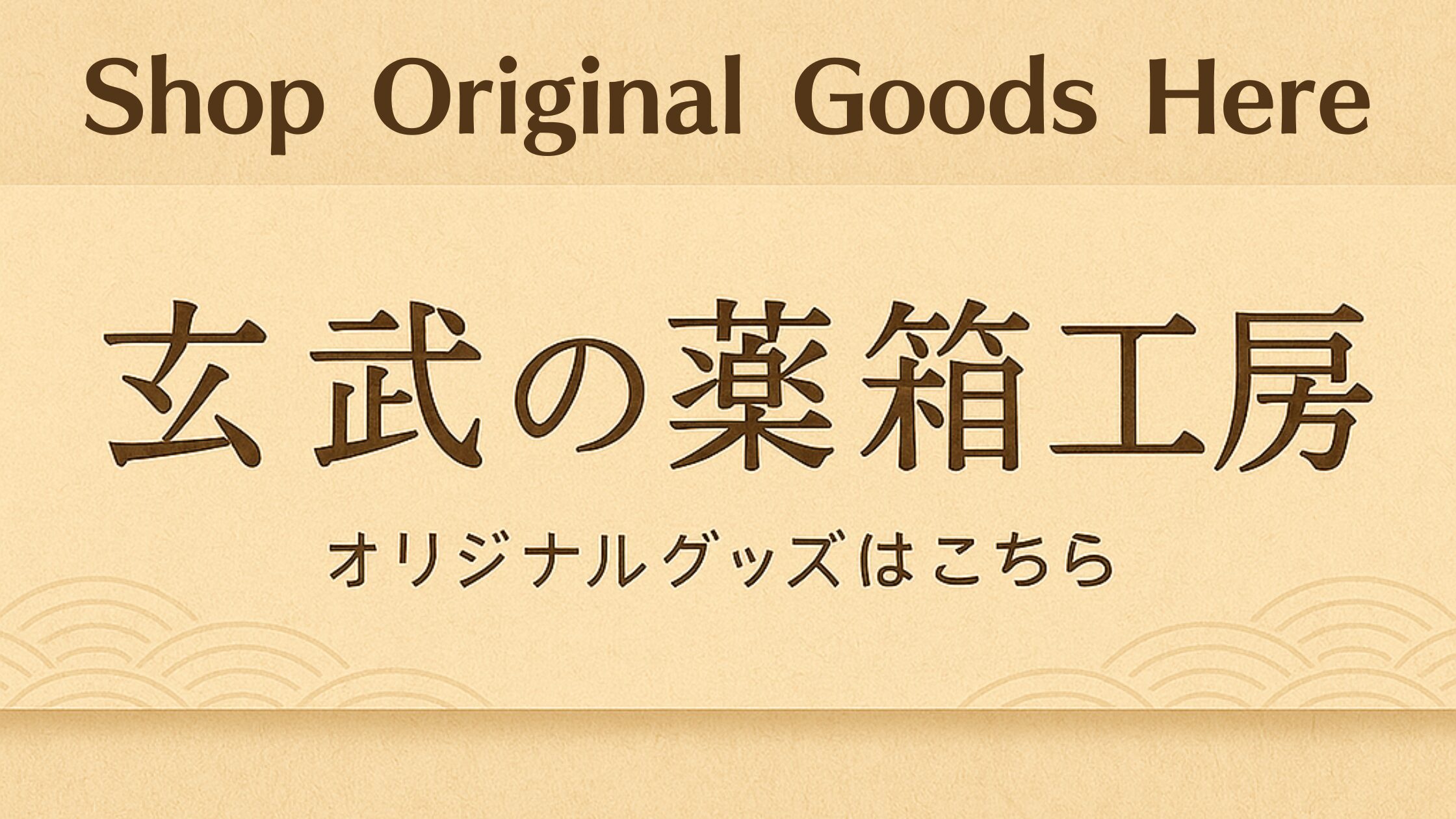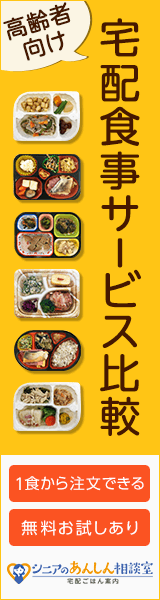防衛の気!『衛気(えき)』を強くしよう!
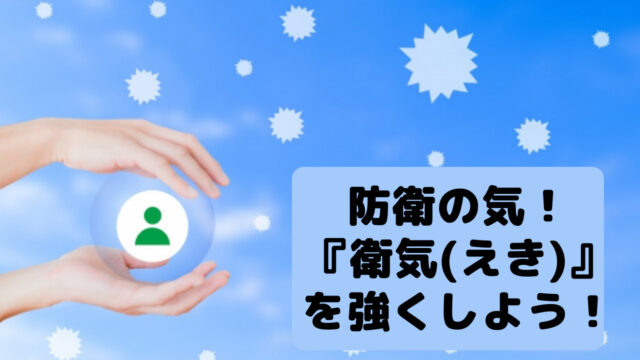
皆さんこんにちは!
漢方薬剤師の玄(@gen_kanpo)です。
春はウイルスや花粉が流行する時期ですね。
漢方薬局には…
『免疫を上げる漢方薬をください!』
こんな相談をされることがあります。
中医学の世界には、
『衛気(えき)』というものが存在します!
この『衛気(えき)』体にとってとても大事な作用をしています。
そこで、今回は上記の問い一つの答えになりえる『衛気(えき)』について解説していこうかと思います。
- 風邪にかかりやすい
- 花粉症の人
- 体が疲れている
- 衛気(えき)とは?
- 衛気(えき)を強化するには
- 衛気(えき)を強くする漢方薬
- 衛気を補えば病気にならない訳では無い!
- まとめ
衛気(えき)とは?
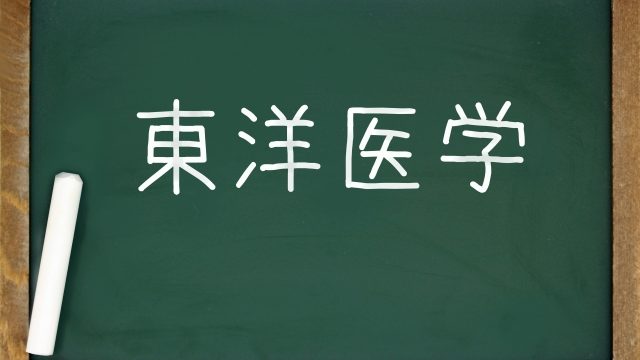
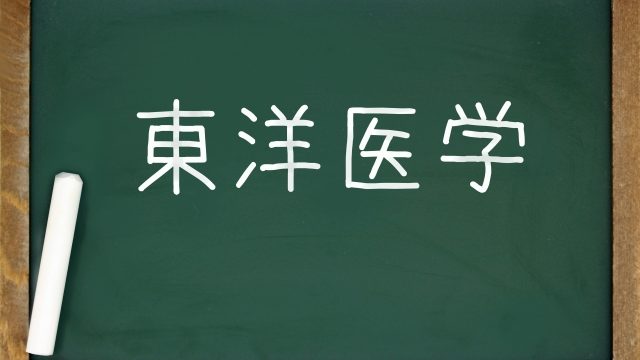
中医学には免疫と似たような意味の言葉で『衛気(えき)』というものがあります。
『衛気(えき)』は気の1つで名前の通り『防衛の気』です。
体表面(皮膚、肌)に存在するとされており
- 体表を守り邪気の侵入を防ぐ
- 汗をコントロールして体温を維持する
- 皮膚や臓腑を温める
こんな作用があります。
この『邪気』には花粉やウイルス、ハウスダストなども含まれると考えられています。
口腔内、鼻、気管支、皮膚などの粘膜を強化するとも考えられており、簡単に言うと体のバリアの働きをしています。
中医学ではこの『衛気』が少ない人を衛気虚といい
- 病気になりやすい
- 暑くないのに汗をかく
- 体温調節が苦手になる
上記の様な症状が出やすいです。
確かに似ているわ~☆
また衛気虚でもう1つ大事な症状は『汗』
汗を大量にかくと体のエネルギー(気・津液)が失われます!
衛気はこれを防いでくれています!
衛気が薄くなると汗を体に留めておく事が出来なくなり漏れ出てしまいます。
この状態はエネルギーを垂れ流しているためどんどん疲れてしまいます。
葛根湯は免疫力を上げる漢方薬ではありません❌
午前中に来店の患者さん
『コロナウイルス流行ってるから免疫力上げるために葛根湯だしてくれたの!』
なんちゅうヤブ……
( >д<)、;’.・ ゲホゴホ葛根湯は汗で風寒の邪気を散らす漢方薬!
不要な人が飲めば逆に免疫力が下がります❌
— 🐢漢方薬剤師 玄🐍 (@gen_kanpo) March 4, 2020
衛気が足りない人に葛根湯なんか飲ませたら絶対ダメ!!
衛気(えき)を強化するには
それでは衛気を強化するにはどうしたらよいのでしょうか?
衛気は『気』の1種です。
気の生成には3ルートあり
- 父母から受け継ぐ(腎)
- 飲食物から(脾)
- 新鮮な空気から(肺)
衛気の生成は脾と腎が関与しています。
脾胃が飲食物から得たエネルギーで腎で生成する。
肺の働きで衛気を全身に散布し外邪の侵入を防ぐ。。
そのため暴飲暴食や疲労などで胃腸の機能が低下すると材料が足りなくなり衛気は作られなくなってしまいます!
衛気を強くするためには胃腸に優しく、バランスの取れた食事を心がけましょう!
これは年末年始の暴飲暴食が原因の1つと考えられてるよ!
衛気(えき)を強くする漢方薬
衛気を強くするには生活の質を上げ胃腸に優しい食事をする事が第一です!
でも、既に衛気が足りない人には時間がかかってしまいます。
そんな時は漢方薬を上手く使って衛気を補いましょう!
衛気(えき)は気の1種なので強化するには『補気薬』というジャンルの漢方薬を使用します。
補気薬の中でも特に黄耆(おうぎ)という生薬が入っている漢方薬が良く使います!
衛気を補えば病気にならない訳では無い!
ここまでの話を聞いていると
『衛気を補っていれば病気にならない!』
勘違いする人がいます!
病気は外から以外にも【内因】【不内外因】という原因があるんだ!
【内因】
- 体質的な虚弱体質
- 感情の過多
【不内外因】
- 飲食物の不衛生、不摂生
- 偏食
- 気血水の滞り
- 疲れ
- 運動不足
この様な事でも起こります!
誰でも衛気を補えば病を防げ訳では無いですから!
まとめ
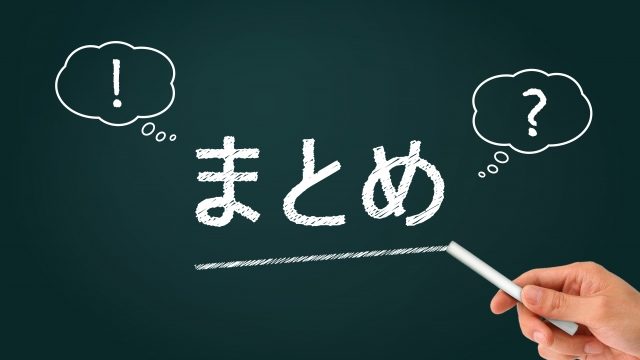
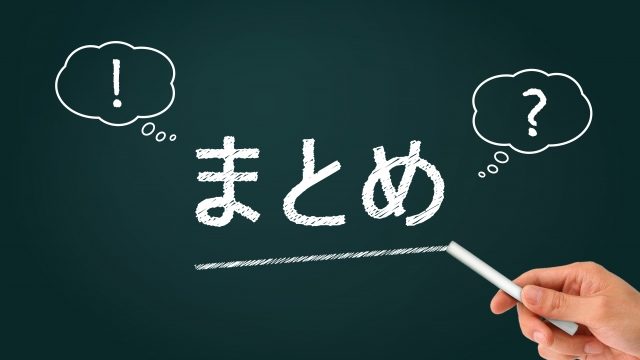
体を邪気から守る
ウイルスや花粉が流行する時期には高めておきたい『気』です。
『衛気』について簡単まとめると
- 衛気は防御の気
- 免疫力と近い意味合い
- 体表を守り邪気の侵入を防ぐ
- 汗をコントロールして体温を維持する
- 皮膚や臓腑を温める
- 衛気を作るには胃腸が大事
- 衛気を作る漢方薬がある
- 衛気を補えば全ての病を防げるわけでは無い
いつもの食事に取り入れる程度がベターだよ!
食事が偏ると衛気は作られなくなるから注意してね!
気をつけま~す☆