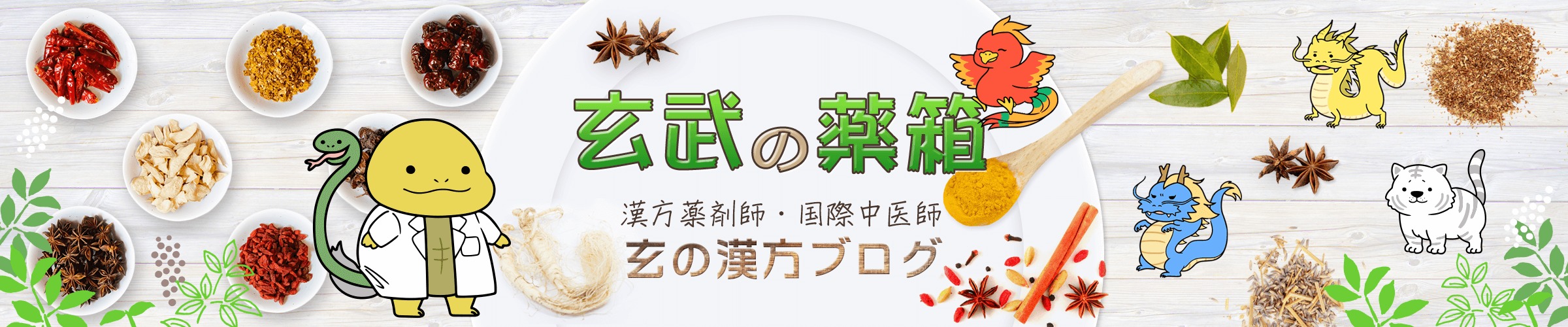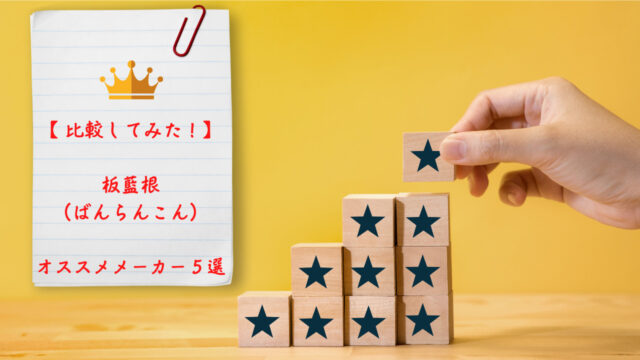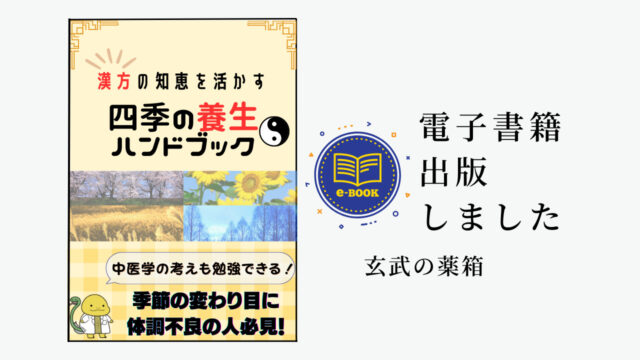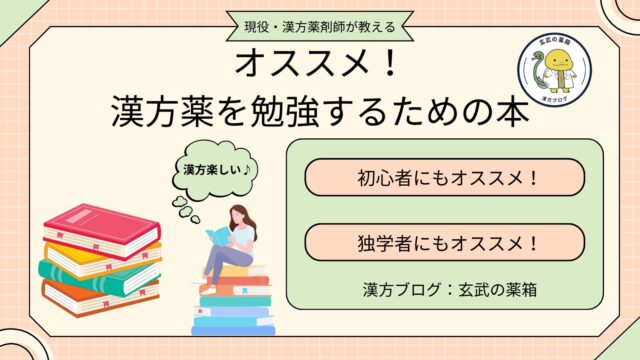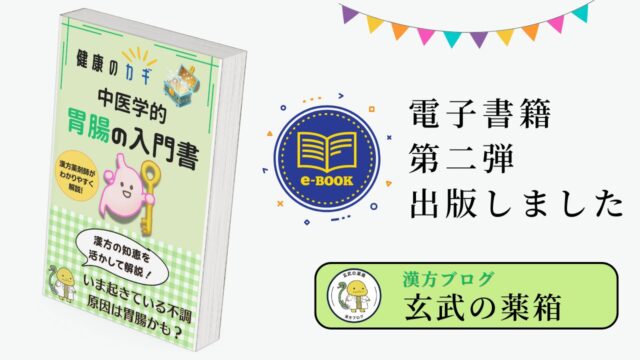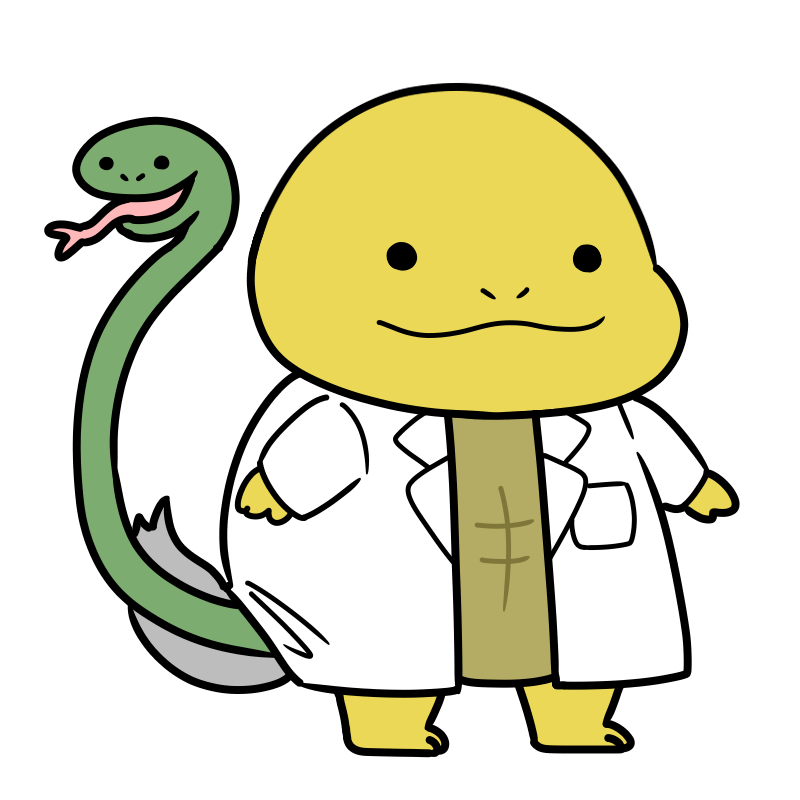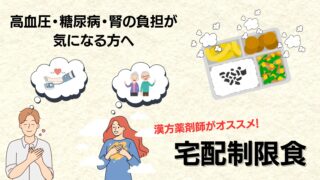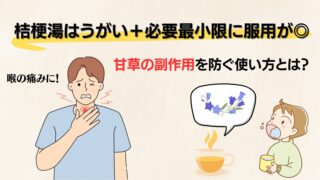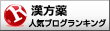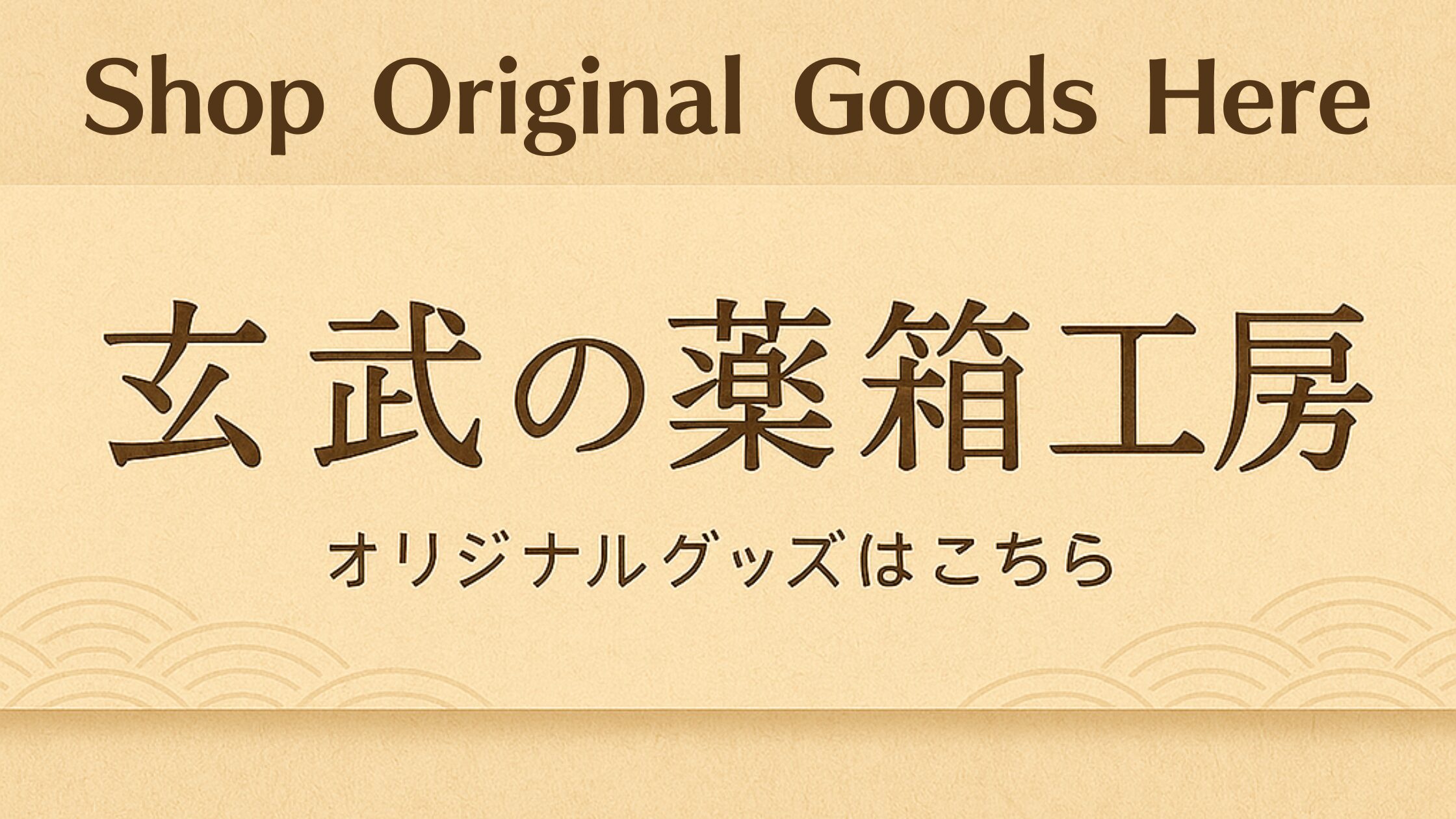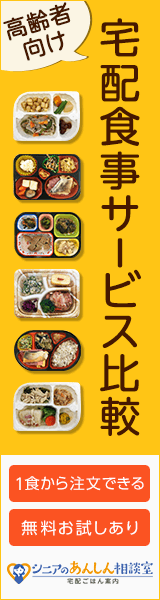私が「漢方薬剤師」になるまでの道のり|薬剤師が東洋医学を学び、仕事にするまで!
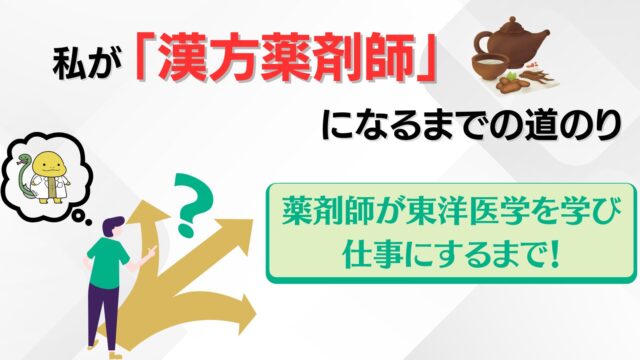
みなさん、こんにちは!
漢方薬剤師の玄(@gen_kanpo)です。
私のブログに来ているという方は、「漢方に興味がある」「体の調子が悪い」といった理由で検索されている方が多いと思います。
その中には、「東洋医学・中医学を仕事にしたい!」という薬剤師・薬学生の方もいるのではないでしょうか?
私も、かつてはその一人でした。
でも、漢方薬の仕事って門戸が極端に狭いんですよね。
そこで今回は、私が漢方薬剤師になるまでの経緯をまとめてみました。
なにかのヒントになれば嬉しいです。
- 漢方薬・中医学を仕事にしたい方
- 薬剤師としての働き方に迷っている方
- 薬剤師としての武器が欲しい方
薬剤師として働く中で感じた「違和感」
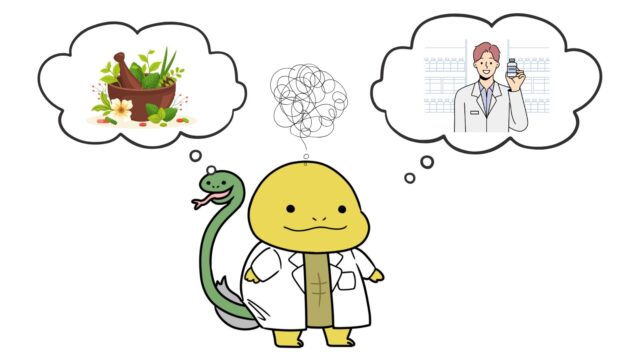
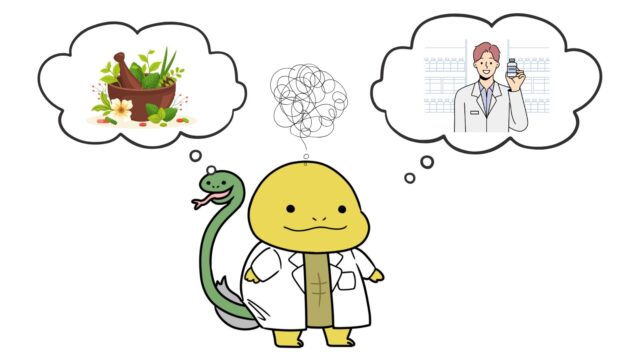
薬剤師としての日々とモヤモヤ
もともと学生の頃から「漢方薬を仕事にしたい」と考えていましたが、最初に就職したのは大手の薬局でした。
理由は、漢方の就職先が全然見つからなかったからです。
大学の就職相談なども活用しましたが、希望に合うものは見つかりませんでした。
また、漢方の仕事でも「これ、本当に薬剤師の就職先?」というような条件のところが多く、自分の理想とは大きなギャップがありました。
就職浪人や中医大学への進学も考えましたが、親に無理を言って薬学部に入れてもらった経緯もあり、「あと数年お給料が出ない」のは現実的に無理だったため、一旦就職することを決めました。
私が最初に就職したのは大手薬局!決めた理由は、カウンセリング力が磨かれそうだったから。
調剤とOTCが併設されていたので、「就職しながら漢方薬の勉強もして、いずれ再就職を目指そう!」という戦略を立てました。
実際に働いてみて感じたのは、「ドラッグストアでは自由にものが売れない」ということ。
自分が「この漢方薬が体質的に合いそう」と考えても、上司からは「推奨品を売ってください」「こっちの方が利益率が高い」といった指示が出ることが多く、やりたいこととのギャップに悩みました。
もちろん、会社としてはそれが当然ですし否定はしません。
ただ、当時の私は強い違和感を覚え、次第にモヤモヤが大きくなっていきました。
特に調剤業務では、「患者さんが胃腸の調子を崩しているように見えるのに八味丸?」「寒熱のバランスが合っていないように思える処方」などに戸惑うこともありました。
そのようなとき、思い切って疑義照会をしたものの、うまく受け入れてもらえず悩んだ経験もあります。
きっかけになった出会いや経験
中医学との出会いは、薬局に届いたカネボウ(現クラシエ)漢方の勉強会の案内がきっかけでした。
「とりあえず何でもいいから勉強会に行こう!」という軽い気持ちで参加したのが最初。
月1回の勉強会で、初級から上級まで段階的に学べる仕組みで、始めての勉強会でもわかりやす買ったのを覚えています。
この勉強会を通じて、「自分は中医学をベースに学んでいこう!」という軸が定まりました。
その頃に使っていたテキストは、今でも大切に保管しています。
そこで聞いた「虚実の考え方」など、自分が思っていた、大学で勉強した漢方(中医学)とはまた違う奥深さを感じ、どんどん惹かれていきました。
就職後2〜3年ほどは、調剤やOTCの仕事を続けながら漢方薬の勉強を継続し、「漢方生薬認定薬剤師」を取得することができました。
この頃から「やっぱり本格的に漢方薬を仕事にしたいな」と強く考えるようになったのを覚えています。
東洋医学を学び始めるまでの試行錯誤
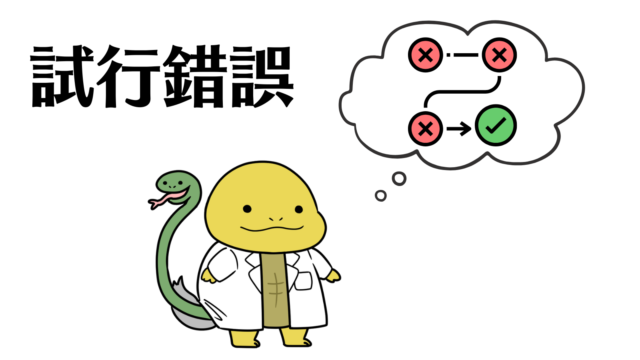
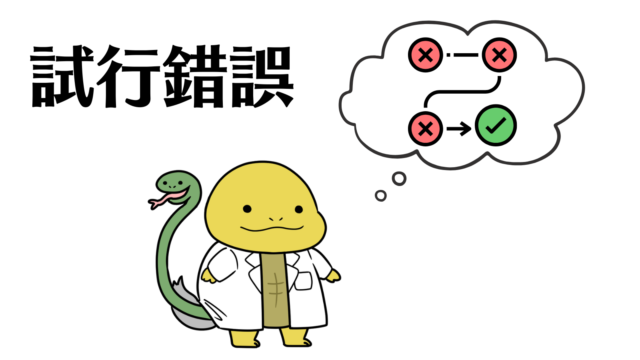
最初に取り組んだ学習法と困ったこと
最初はとにかく「生薬学(中薬学)」を勉強しました。
ある先生が「中薬学は英語でいう英単語。単語がわかれば全体の意味も見える」と言っていたのが心に残り、必死で覚えました。
後に国際中医師(国際中医専門員)の免許を取ることになりますが、中薬学は自信を持って受験できた分野です。
また、調剤の仕事と並行して生薬学・中薬学を学んだことで、知らない漢方薬の処方に出会っても、添付文書から構成生薬を確認すれば、処方全体の方向性や狙いがわかるようになっていきました。
仕事をしながらでも漢方の理解が深まり、当時の調剤業務にも「漢方的視点での読み解き」が加わることで、より深みが出てきたように感じます。
生薬を「覚えるべき知識」としてだけでなく、「実際の処方を理解する道具」として使えるようになってからは、学ぶことがますます楽しくなっていきました。
漢方薬局・講座・資格取得などのリアル
勉強会の探し方は「自分が中医学をベースにする」と決めたことで、かなりスムーズになりました。
コタロー漢方の勉強会によく参加し、講義や書籍に投資していました。
ただし、勉強会は土日が多く、しかも地方開催のこともあったため、泊まりがけになることも。
参加費も1回1万円、年間10万円など高額で、書籍も高いものが多く、20代の私はほとんどの給料と時間を漢方の勉強に費やしていました。
初心者・独学者にもオススメ!現役漢方薬剤師がオススメする漢方薬を勉強するための書籍
現在はオンラインやウェビナーが普及し、遠方の方や地方の勉強会でも参加しやすくなっています。
講師として登壇する立場になった今では「反応を見たい気持ち」も理解できますが、当時と比べて現代の学習環境は恵まれていると思います。
「漢方薬剤師」として働く


私が現在の漢方専門薬局に入社したのは、転職サイトを利用したのがきっかけでした。
数年は我慢しようと思い「漢方薬局への就職経験がない」という条件で探していたところ、数ヶ月後に良縁に巡り会いました。
担当者さんには「めったにないですよ!」といわれ、面接→即採用というミラクルを引き当てました。
その後、色んな人に話を聞きますが、私のようなケースは極稀です。
漢方の知識を仕事に活かすには?
漢方薬や東洋医学の知識は、薬剤師としての日常業務にも大いに活かせます。
なぜなら、東洋医学の考えでは病に対して漢方薬だけでは治しきれないからです。
薬はあくまでツールの一つであり、養生や生活指導が重要になります。
特に重要だと感じている養生は「食事・睡眠・適度な運動」。
体質に合った漢方薬でも、生活が乱れていれば効果は限定的です。
たとえば、頭痛や生理痛に対して「鎮痛剤を飲めば痛みがすぐに和らぐ」ことはあります。
でも、それは“治った”と言えるのでしょうか?
鎮痛剤を飲めば、睡眠不足でも食事が乱れていても痛みは軽減され、あたかも治ったように感じます。
一方、東洋医学では「なぜ痛みが起きたのか?」という原因に目を向けます。
疲労や胃腸虚弱が原因であれば、まずは胃腸を整える漢方薬を使います。
このとき、食生活や睡眠の乱れが続いていれば、漢方薬の効果も十分に発揮されないでしょう。
この言葉は食に限定されていますが、睡眠も適度な運動も「医」となりうると私は考えます。
東洋医学を学ぶと「養生=生活の質の向上」について深く考えるようになります。
これは西洋医学の現場でも活かせる視点です。
たとえば調剤薬局でも患者さんへの一言アドバイスに活かせますし、OTCでは健康食品や健康グッズの提案につなげることもできます。
実際の働き方
漢方専門薬局に入ってすぐ、勉強してきたことが現場では通用しないことを痛感。
- 教科書通りのお客さんはいない
- 虚実・寒熱・表裏が複雑に混在
- 「話を聞くけど鵜呑みにしない」
そんな現場で、先輩の処方を観察し、接客技術や生薬の実物を通じて学びました。
実際に生薬や漢方薬に触れることは、学びを深めるうえで非常に効果的でした。
匂いを嗅いでみる、手に取って観察するなど、五感を使って体験すると、知識が格段に頭に入りやすくなります。
今では学生や後輩にも「まず触れてみる」「数年だけでも修行と思って飛び込んでみては?」と伝えています。
さらに、「この生薬、先輩がよく使っているな」と気づいたときは、自分なりに調べて使い方を考えてみるようにしました。
実際に使ってみることで、座学では得られない気づきが多く、非常に勉強になりました。
そして、実際の現場で働いて感じたことは、中医学や漢方薬の知識だけでなく、カウンセリングや一般常識、接客技術なども大切だということです。
「お客さんが何に困っているのか?」
「話しにくい雰囲気を出していないか?」
「相談しにくい内容なのか?」
「言葉選びは間違っていないか?」
中には「知識があればそれで良い」と考える方もいるかもしれません。
ただ、私はそうは思いません。
漢方薬局や薬店に来る方の中には、病院や一般的な治療でうまくいかなかったり、心身ともにダメージを受けている方も多いです。
そうした方々の気持ちを汲む力は、相談者としてとても重要です。
この考えは、実際に現場で働くうちに自然と身についたものでした。
だからこそ、これから漢方薬を学びたいと考えている方の中で、すでに接客業や医療現場で働いている方は、ゼロからのスタートではありません。
今の職場で培った接客やコミュニケーションの技術は、漢方相談でも必ず活かされます。
「人と人との信頼関係」が治療効果にも影響する大切な要素のひとつだからです。
やりがい
お客さんの不調が少しでも改善し、「なんとなく体がラクになりました」と言っていただけたときは、やはりとても嬉しいです。
特に嬉しいのは、漢方薬を継続的に服用していた方が「もう飲まなくても大丈夫そうです」と卒業されるとき。
売上的には少し寂しい気持ちもありますが(笑)
「ここに来てよかった」「玄先生に相談してよかったです」と言っていただけると、「この仕事を続けてきて本当によかったな」と心から思えます。
もちろん、いいことばかりではありません。
漢方薬はお世辞にも安価とは言えないものも多く、ご相談者の期待に応えられるかどうか、常にプレッシャーを感じています。
時には自分の力不足を痛感することもあり、帰宅後も調べものをしたり、頭の中で処方の可能性をぐるぐる考え続けてしまうこともあります。
それでも、「目の前の人が少しでもラクになるように」という想いが、日々の原動力になっています。
一人ひとりと丁寧に向き合いながら、寄り添えること。
これから目指す人へのヒント
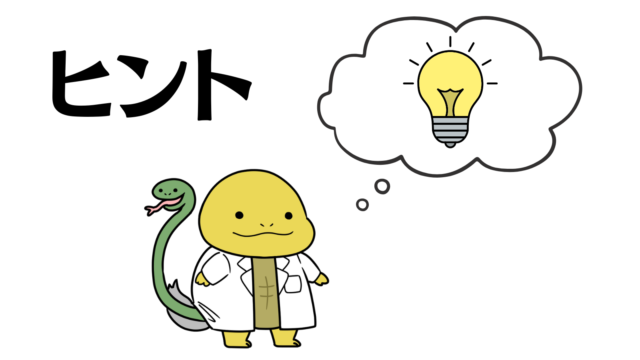
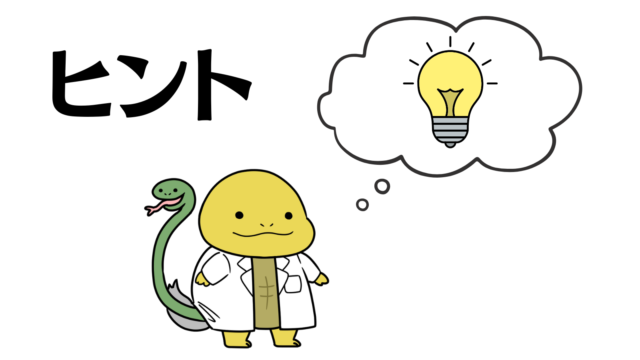
漢方業界は就職先が少なく、条件も厳しいこともあります。
無理にブラックな職場に飛び込む必要はありません。
まずは、勉強会や書籍などを通して、興味のある分野から少しずつ学んでみてください。
漢方の世界は狭く、真面目に勉強を続け実力をつけていけば、人を通して思いがけないご縁や就職口が見つかることもあります。
いきなり大きな一歩を踏み出さなくても大丈夫。
まずは勉強会に参加したり、SNSで情報を発信したりと、できることから始めてみてください。
そして、インプットも大事ですが、アウトプットも同じくらい大切です。
最初は漢方相談でなくても大丈夫。
SNSやブログなどで、自分の学んだことや考えを発信することで、同じ考えを持つ仲間や、将来のファンに出会えるかもしれません。
小さな一歩でも、それが未来につながる大切な一歩になります。
おわりに
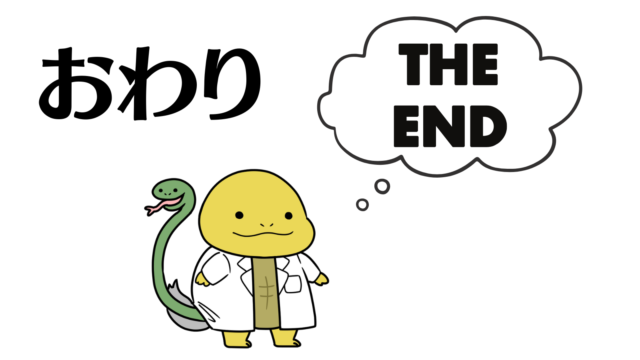
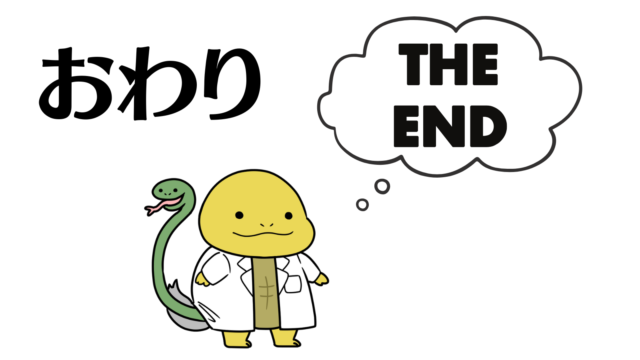
ここまで読んでいただきありがとうございます。
日本全体で少子高齢化が進む中、漢方業界もまた、後継者不足や若い世代にとっての敷居の高さといった課題を抱えています。
その影響で、後継者が見つからず閉業を選ぶ薬局や薬店も増えてきました。
だからこそ、これから漢方を学ぼうとしている薬剤師や学生の存在は、業界にとって大きな希望です。
私も15年以上、この業界の末端で活動してきました。
少しでも多くの方が、漢方薬・東洋医学に興味を持ち、仕事にしたいと思ってくれるように、今後もブログ、電子書籍、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)、noteなどで発信を続けていきます。
オリジナルグッズなども販売中です。
何か気になることがあれば、お気軽にコメントやメールでご相談ください。